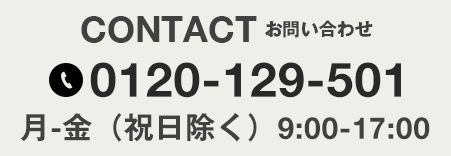- 無垢フローリング・無垢材|マルホンHOME
- > 木材の基礎知識
- > ウッドデッキの施工上および使用上のポイント
ウッドデッキの施工上および使用上のポイント
今や一般的な戸建て住宅においても標準化されつつあるほど、人気が定着しているウッドデッキ。
オープンエアーの開放感を味わえる“第二のリビング”としての機能性や、外観にアクセントを与える意匠性など、住まいにプラスアルファを付加します。無垢材という「生きている素材」を屋外という苛酷な環境にさらすだけに、無垢材特有の施工上および使用上のノウハウを知っておくと施工・使用の場面に役立ちます。
施工上のポイント
①木口の割れを防ぐ
木材は周囲の環境に合わせて水分を吸収・放出しますが、その量は部位によって異なります。水分の浸透・蒸発は、他の部分に比べて木口でより多く起こります。木口面からの浸透性は柾目面・板目面と比較して、数十倍にも達するとも言われているほどです。水分の抜けた木口では急速に縮もうとするのに対し、水分が残っている内部ではその動きに逆らうため、木口付近に無理が生じ、割れが起こりやすくなります。
あらかじめデッキ材の木口に割れ止め剤を塗り、コーティングしておくことで、木口からの偏った水分の蒸発を抑え、その結果、割れを防ぐことができます。一般的な割れ止め剤は、木工用ボンドのような形状で、透明な皮膜をつくります。
②膨張を防ぐ
耐久性の高い木材を利用してもデッキも無垢材です。デッキの下部に水分や湿気がたまると、それをデッキ材が吸収し、膨張の原因になることがあります。
そのため、デッキの基礎床面には勾配をつけ、雨水などが排出されるようにしておきます。
また、デッキを長持ちさせるには、木口と木口がぴったりと隙間なく重ならないように、施工することがポイントです。隙間なく施工すると、水分が抜けにくく、“腐り”の原因になりかねません。
③ビス打ちは穴をあけて
デッキに使用する材は、硬く、密度の高いタイプが用いられています。こうした材の場合、無理にビスを打ち込むと、割れてしまうことがあります。
そのため、デッキ材を固定する際には、あらかじめ下穴をあけておき施工することをおすすめします。
当社の「GRKスクリュー(高性能ネジ)」は、ネジ構造に工夫がされており、硬い材に使用するとネジ打ち労力を著しく軽減させることができるため、デッキ材として使われる非常に硬い木材の施工に効力を発揮する商品です。
くわしくはこちらをクリック

デッキ 施工イメージ
イペ
使用時のポイント
①乾燥割れの処置
木材は「生き続けている素材」であるため、温度・湿度といった環境変化に応じて膨張収縮を繰り返しています。その結果、木材表面に細かな割れ、いわゆる「乾燥割れ(干割れ)」を生じます。木材の強度を損なうのでは、との心配もあるかもしれませんが、乾燥割れは表面のみに起こる現象であり、強度に影響を与えないという研究結果が報告されています。
しかし、美観的に乾燥割れはマイナス要因となるため、割れを抑えられるタイプの塗料を使用すれば、軽減できます。当社の外装用自然塗料「Arbor外装用クリアーオイル」は、木材内部の繊維に深く浸透して細胞一つ一つを保護するタイプの塗料ですので、表面の乾燥割れを最小限に抑える効果を備えています。
くわしくはこちらをクリック
②色の染み出しの処置
木材のなかには水に浸けられると色が染み出すものがあります。これを「溶脱」といいます。
常に風雨にさらされているデッキ材を選ぶ際には、この溶脱の度合いを知った上で、それが周囲に及ぼす影響も考慮に入れておく必要があります。特に2階部分に施工する場合や白い壁の付近に施工する場合にはご注意ください。
なお、デッキ材から溶脱した色が周囲の白壁などを汚してしまった場合、界面活性剤入りの洗剤を使用してブラシでこすれば簡単に落とすことができます。
ちなみに、ウリンは溶脱しやすく、セランガンバツー、マニルカラはほとんど溶脱しません。
イペは溶脱をしますが、周囲に著しく影響を及ぼすほどではありません。白い壁付近に施工する場合は、注意を要しますが、コンクリート等色つきの壁の場合は問題ないでしょう。
③変色の処置
木材はどんな樹種でも経年変化により灰色に変色します。どうしても変色を防ぎたい場合は、顔料を含んだエナメル塗料やウレタン塗料で塗装することである程度防ぐことができます。しかし、直接風雨にさらされるため、塗装の劣化はさけられません。定期的に塗りなおしが必要になります。
最近では、この灰色への変色を他にはない“味”として積極的に捉え、あえて意匠的に活かすケースも増えています。
④塗装の塗り替え
木材に水分が多く含まれているまま塗装すると、塗装の内部でカビなどが発生する原因になります。そのため、塗り替えを行う際は、晴れた日が何日か続いた後に実施してください。含水率が20%以下が目安です。

経年変化の例
紫外線の影響で木材はどんな樹種でも灰色に変化します。
今や一般的な戸建て住宅においても標準化されつつあるほど、人気が定着しているウッドデッキ。
オープンエアーの開放感を味わえる“第二のリビング”としての機能性や、外観にアクセントを与える意匠性など、住まいにプラスアルファを付加します。無垢材という「生きている素材」を屋外という苛酷な環境にさらすだけに、無垢材特有の施工上および使用上のノウハウを知っておくと施工・使用の場面に役立ちます。
オープンエアーの開放感を味わえる“第二のリビング”としての機能性や、外観にアクセントを与える意匠性など、住まいにプラスアルファを付加します。無垢材という「生きている素材」を屋外という苛酷な環境にさらすだけに、無垢材特有の施工上および使用上のノウハウを知っておくと施工・使用の場面に役立ちます。
施工上のポイント
①木口の割れを防ぐ
木材は周囲の環境に合わせて水分を吸収・放出しますが、その量は部位によって異なります。水分の浸透・蒸発は、他の部分に比べて木口でより多く起こります。木口面からの浸透性は柾目面・板目面と比較して、数十倍にも達するとも言われているほどです。水分の抜けた木口では急速に縮もうとするのに対し、水分が残っている内部ではその動きに逆らうため、木口付近に無理が生じ、割れが起こりやすくなります。
あらかじめデッキ材の木口に割れ止め剤を塗り、コーティングしておくことで、木口からの偏った水分の蒸発を抑え、その結果、割れを防ぐことができます。一般的な割れ止め剤は、木工用ボンドのような形状で、透明な皮膜をつくります。
木材は周囲の環境に合わせて水分を吸収・放出しますが、その量は部位によって異なります。水分の浸透・蒸発は、他の部分に比べて木口でより多く起こります。木口面からの浸透性は柾目面・板目面と比較して、数十倍にも達するとも言われているほどです。水分の抜けた木口では急速に縮もうとするのに対し、水分が残っている内部ではその動きに逆らうため、木口付近に無理が生じ、割れが起こりやすくなります。
あらかじめデッキ材の木口に割れ止め剤を塗り、コーティングしておくことで、木口からの偏った水分の蒸発を抑え、その結果、割れを防ぐことができます。一般的な割れ止め剤は、木工用ボンドのような形状で、透明な皮膜をつくります。
②膨張を防ぐ
耐久性の高い木材を利用してもデッキも無垢材です。デッキの下部に水分や湿気がたまると、それをデッキ材が吸収し、膨張の原因になることがあります。
そのため、デッキの基礎床面には勾配をつけ、雨水などが排出されるようにしておきます。
また、デッキを長持ちさせるには、木口と木口がぴったりと隙間なく重ならないように、施工することがポイントです。隙間なく施工すると、水分が抜けにくく、“腐り”の原因になりかねません。
耐久性の高い木材を利用してもデッキも無垢材です。デッキの下部に水分や湿気がたまると、それをデッキ材が吸収し、膨張の原因になることがあります。
そのため、デッキの基礎床面には勾配をつけ、雨水などが排出されるようにしておきます。
また、デッキを長持ちさせるには、木口と木口がぴったりと隙間なく重ならないように、施工することがポイントです。隙間なく施工すると、水分が抜けにくく、“腐り”の原因になりかねません。
③ビス打ちは穴をあけて
デッキに使用する材は、硬く、密度の高いタイプが用いられています。こうした材の場合、無理にビスを打ち込むと、割れてしまうことがあります。
そのため、デッキ材を固定する際には、あらかじめ下穴をあけておき施工することをおすすめします。
当社の「GRKスクリュー(高性能ネジ)」は、ネジ構造に工夫がされており、硬い材に使用するとネジ打ち労力を著しく軽減させることができるため、デッキ材として使われる非常に硬い木材の施工に効力を発揮する商品です。
くわしくはこちらをクリック
デッキに使用する材は、硬く、密度の高いタイプが用いられています。こうした材の場合、無理にビスを打ち込むと、割れてしまうことがあります。
そのため、デッキ材を固定する際には、あらかじめ下穴をあけておき施工することをおすすめします。
当社の「GRKスクリュー(高性能ネジ)」は、ネジ構造に工夫がされており、硬い材に使用するとネジ打ち労力を著しく軽減させることができるため、デッキ材として使われる非常に硬い木材の施工に効力を発揮する商品です。
くわしくはこちらをクリック

デッキ 施工イメージ
イペ
使用時のポイント
①乾燥割れの処置
木材は「生き続けている素材」であるため、温度・湿度といった環境変化に応じて膨張収縮を繰り返しています。その結果、木材表面に細かな割れ、いわゆる「乾燥割れ(干割れ)」を生じます。木材の強度を損なうのでは、との心配もあるかもしれませんが、乾燥割れは表面のみに起こる現象であり、強度に影響を与えないという研究結果が報告されています。
しかし、美観的に乾燥割れはマイナス要因となるため、割れを抑えられるタイプの塗料を使用すれば、軽減できます。当社の外装用自然塗料「Arbor外装用クリアーオイル」は、木材内部の繊維に深く浸透して細胞一つ一つを保護するタイプの塗料ですので、表面の乾燥割れを最小限に抑える効果を備えています。
くわしくはこちらをクリック
木材は「生き続けている素材」であるため、温度・湿度といった環境変化に応じて膨張収縮を繰り返しています。その結果、木材表面に細かな割れ、いわゆる「乾燥割れ(干割れ)」を生じます。木材の強度を損なうのでは、との心配もあるかもしれませんが、乾燥割れは表面のみに起こる現象であり、強度に影響を与えないという研究結果が報告されています。
しかし、美観的に乾燥割れはマイナス要因となるため、割れを抑えられるタイプの塗料を使用すれば、軽減できます。当社の外装用自然塗料「Arbor外装用クリアーオイル」は、木材内部の繊維に深く浸透して細胞一つ一つを保護するタイプの塗料ですので、表面の乾燥割れを最小限に抑える効果を備えています。
くわしくはこちらをクリック
②色の染み出しの処置
木材のなかには水に浸けられると色が染み出すものがあります。これを「溶脱」といいます。
常に風雨にさらされているデッキ材を選ぶ際には、この溶脱の度合いを知った上で、それが周囲に及ぼす影響も考慮に入れておく必要があります。特に2階部分に施工する場合や白い壁の付近に施工する場合にはご注意ください。
なお、デッキ材から溶脱した色が周囲の白壁などを汚してしまった場合、界面活性剤入りの洗剤を使用してブラシでこすれば簡単に落とすことができます。
ちなみに、ウリンは溶脱しやすく、セランガンバツー、マニルカラはほとんど溶脱しません。
イペは溶脱をしますが、周囲に著しく影響を及ぼすほどではありません。白い壁付近に施工する場合は、注意を要しますが、コンクリート等色つきの壁の場合は問題ないでしょう。
木材のなかには水に浸けられると色が染み出すものがあります。これを「溶脱」といいます。
常に風雨にさらされているデッキ材を選ぶ際には、この溶脱の度合いを知った上で、それが周囲に及ぼす影響も考慮に入れておく必要があります。特に2階部分に施工する場合や白い壁の付近に施工する場合にはご注意ください。
なお、デッキ材から溶脱した色が周囲の白壁などを汚してしまった場合、界面活性剤入りの洗剤を使用してブラシでこすれば簡単に落とすことができます。
ちなみに、ウリンは溶脱しやすく、セランガンバツー、マニルカラはほとんど溶脱しません。
イペは溶脱をしますが、周囲に著しく影響を及ぼすほどではありません。白い壁付近に施工する場合は、注意を要しますが、コンクリート等色つきの壁の場合は問題ないでしょう。
③変色の処置
木材はどんな樹種でも経年変化により灰色に変色します。どうしても変色を防ぎたい場合は、顔料を含んだエナメル塗料やウレタン塗料で塗装することである程度防ぐことができます。しかし、直接風雨にさらされるため、塗装の劣化はさけられません。定期的に塗りなおしが必要になります。
最近では、この灰色への変色を他にはない“味”として積極的に捉え、あえて意匠的に活かすケースも増えています。
木材はどんな樹種でも経年変化により灰色に変色します。どうしても変色を防ぎたい場合は、顔料を含んだエナメル塗料やウレタン塗料で塗装することである程度防ぐことができます。しかし、直接風雨にさらされるため、塗装の劣化はさけられません。定期的に塗りなおしが必要になります。
最近では、この灰色への変色を他にはない“味”として積極的に捉え、あえて意匠的に活かすケースも増えています。
④塗装の塗り替え
木材に水分が多く含まれているまま塗装すると、塗装の内部でカビなどが発生する原因になります。そのため、塗り替えを行う際は、晴れた日が何日か続いた後に実施してください。含水率が20%以下が目安です。
木材に水分が多く含まれているまま塗装すると、塗装の内部でカビなどが発生する原因になります。そのため、塗り替えを行う際は、晴れた日が何日か続いた後に実施してください。含水率が20%以下が目安です。

経年変化の例
紫外線の影響で木材はどんな樹種でも灰色に変化します。